
朋優学院高等学校様 活用事例 Monoxerを用いた「自走力」の醸成|適度なペース設計と声のかけ方が鍵
導入組織について
東京都品川区に所在する朋優学院高等学校。首都圏の私立進学校では比較的珍しい、中等部を持たない高等学校だけの単独校です。 近年、急激に難関大への合格実績を伸ばしている学校の1つで、2025年の大学合格実績を見ると、私大の最難関である早慶(早稲田大・慶應義塾大)への合格者は105人で、10年前と比べると5倍以上に増えています。 さらに、人気の高い上理MARCH(上智大、東京理科大、明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大)の私大群について見ると、今年の合格者数は853人、10年前と比べたときの増加数は600人で、いずれも全国トップクラス。近年の卒業生について見ると、大学への現役合格率はほぼ100%(平均97%)、現役進学率は約90%となっています。 |
活用サマリ
Monoxer活用シーン/科目 | ・学年:1年生〜3年生 |
|---|---|
導入目的 | ・基礎学力の徹底を通じて、学習習慣の定着と志望校合格を支援するため。特に生徒一人ひとりが自分で学習計画を立て、自発的に取り組む「自走力」を育むため。 |
課題 | ・学力帯やクラスによって学習への取り組みの差が大きく、英語語彙の習得や日々の学習習慣が教員依存になりやすいこと。また、授業外での学習を持続させる環境作りが課題だった。 |
取り組み | ・Monoxerを導入し、英語を中心に学習範囲を日割りで配信。学習進捗を可視化することで、生徒が自分のペースで学べる環境を整え、教員は面談や定期確認で声かけを行う。社会科や国語科も補助的に活用し、学校全体で習慣化を支援。 |
効果 | ・定期考査の語彙問題で8割以上の得点率を維持するなど、学力向上が定量的に確認できる。さらに、学習進捗の可視化により生徒は自発的に取り組む習慣を獲得し、「日々の積み重ね」の重要性を体感。資格試験合格など、成果の具体例も増加。 |
今回お話を伺った方

今井翼先生(英語科)
・現在担当されているお仕事
- 校務分掌:進路指導部
- システム管理部:教科:英語科副主任
・領域について
- クラス担任では国公立大学を志望する生徒を中心とする集団を対象に担当。
- 科目は論理・表現を中心に担当。語彙指導や英語学習法など、科目に囚われず英語全般への向き合い方を指導。
・お仕事で大切にされていること
-「何を目的・目標に据えて、目の前の学びに向き合っているかを常に生徒と共有すること」
・ご家族構成、ご趣味、休日の過ごし方、マイブームなど
- 家族は妻と息子の3人、趣味は英語学習、休日は読書、映画鑑賞、英語学習、旅行などをしてリラックスしています。マイブームは現2歳の息子と電車について学び、電車で旅すること
【導入目的】自走力を育むための基礎学力徹底と学習環境づくり
―はじめに、御校が大切にされている教育方針について教えてください。
―今井先生
私たちは「自立と共生」を理念に掲げています。特に「自立」を非常に重視しており、生徒が自分の力で学びを進め、進路を切り拓ける力、いわば「自走力」を養うことを目標にしています。
本校には、公立高校を第一志望にしていたけれど惜しくも届かず、併願で入学する生徒も多いんです。そうした生徒に「もう一度自信を取り戻させたい」「コツコツ積み重ねることの大切さを伝えたい」と考えています。
そのために欠かせないのが基礎学力の徹底です。土台がしっかりしてこそ、応用力や思考力も育ちますし、最終的に難関大合格にもつながる。私たちはそこを教育の柱に据えています。
―ありがとうございます。「自走力」について、より詳しく伺ってもよろしいでしょうか。
―今井先生
端的に言えば「自分で目標を定めて、そこに向かって動き出す力」ですね。本校は進学校化を目指し、大学進学の成果も出てきていますが、その過程で生徒自身が「どんな大学に行きたいのか」「そのために何をすべきか」を考える機会が多くあります。
特に数学などでは、厳しい現実に直面する生徒も少なくありません。その中で「自分にできることは何か」「自分は何をやりたいのか」を見極め、適性と願望の間で折り合いをつけながら、自分なりの目標を決めて進んでいく。これこそが自走力だと思います。
我々教員の役割は、その目標に到達するために「どのくらいの量をこなす必要があるか」「どんな方向性を取るべきか」を示し、スピードやペースを一緒に伴走してあげることです。最終的に走るのは生徒自身ですので、そのための力を養う仕組みを1年次から面談や日々の学習を通じて整えています。
Monoxerもまさにその土台づくりに寄与していると思います。特に1年次で自らMonoxerに取り組む姿勢が身についていれば、2年次以降も自然と取り組めるように感じます。
―Monoxer導入前の課題とMonoxer導入のきっかけをお聞かせください。
―今井先生
導入前は特に英語の語彙学習において、教員やコースごとに取り組みの差が生じることが課題でした。学力帯の高いコースは着実に進められる一方で、低いコースでは取り組みが甘くなりやすく、成績にも直結していました。また、授業中に単語帳を開かせる頻度や声掛けの仕方なども教員の裁量に委ねられ、属人化や二極化が進んでいたんです。
すべてのコースで再現性のある学習環境をつくる必要があると感じていたときに、Monoxerを知る機会がありました。2021年に一部クラスでトライアルを実施したところ、成果が顕著に表れたため「これは全校で活用すべきだ」と判断し、翌年度から本格導入に踏み切りました。より良い教育を実現できるという期待感が導入の大きな後押しとなりました。
―様々な候補もあるなか、Monoxerを選んだ決め手は何でしたか?
―今井先生
実は過去にも暗記アプリを試したことはありましたが、クラス単位での学習進捗を可視化できず、実用性に乏しい点が課題でした。その点Monoxerは、生徒個人だけでなくクラス全体の進捗を一覧でき、担任や教員が「各生徒の進捗」を簡単に把握できます。
さらに、生徒にとっても使いやすく、記憶度に応じて出題形式を自動で調整してくれるため、学習のハードルが下がります。教員側にとっては集計や指導の効率化が図れること、生徒にとっては無理なく続けられる設計であること、この両面を兼ね備えている点が大きな決め手でした。「管理のしやすさ」と「生徒のとっつきやすさ」を両立できている点はMonoxerならではの強みだと感じています。

【効果実感】語彙力向上と学習習慣の定着がもたらす成果
―実際にMonoxerを導入して、どのような成果がありましたか?
―今井先生
定量的に一番わかりやすいのは、語彙問題の得点率です。定期考査の語彙問題では常に8割以上を超えるようになりました。しかも出題する単語は「これは間違えるだろう」という難しいものを選んでいるのですが、それでも平均して高得点が取れるようになっています。
資格試験でも成果が見えています。以前なら合格は難しいと思っていた生徒が、実際に受かるようになってきました。これは教師としても驚きで、学習習慣の定着が力になっていると実感します。
―定量的な成果だけでなく、生徒の姿勢にも変化はありましたか?
―今井先生
はい、定性的な効果も大きいです。Monoxerを通して学習状況が可視化されることで、担任の先生と教科担当の両方が連携しやすくなりました。二重、三重で声かけできるので、生徒は「やらざるを得ない環境」に自然と置かれる。これが習慣化を後押ししています。
―生徒の「自走力」を育むうえでも、Monoxerは役立っていますか?
―今井先生
そうですね。成績をつける際に日割りで課題の進捗を確認し、無理のないペースで取り組めるようにしています。コツコツ続けている生徒は記憶の定着も良いのですが、逆に直前にまとめてやる子は成果が出にくい。その違いを本人たちが自然と実感し、友達同士でも「やっぱり毎日やる方が力になるよね」と共有しているんです。
こうした成功と失敗の両面の体験が、生徒にとって「日々の積み重ねが正しい」という価値観を育てています。これはまさに自走力の根幹であり、Monoxerのおかげで自然に身についていく。教員側もその気づきを生徒指導に活かせるので、テクノロジーと人間が手を取り合っている感覚があります。
実際、生徒の中に「コツコツやらないと力にならない」という意識が少しずつ浸透してきました。最後の数日で一気にやる子もいますが、結果が伴わないことを体感する。逆に日々の積み重ねが成果につながることを実感する。その繰り返しが自走力を育てているんだと思います。
【活用方針】英語を軸にした学習習慣の定着と全校での支援体制
―どの教科で、どのような目的でMonoxerを活用しているのでしょうか。
―今井先生
中心となっているのは英語の単語学習です。英語は文系・理系を問わず必ず必要になるため、どの担任からも生徒に働きかけやすいので。特に1年次は「毎日コツコツ取り組むことの大切さ」を体得する時期なので、英語を軸に学習習慣を根付かせる狙いがあります。
そこに相乗りするかたちで、社会科や国語科も一部の教材を配信しています。社会では地歴公民を中心に、自分のペースで進めたい生徒には紙のノートや一問一答形式なども認めつつ、Monoxerを補助的に活用しています。
―具体的なタスク配信の方法はどのようにされていますか。
―今井先生
基本的には「定期考査ごとにやるべき範囲」を決め、そこを日割りにして提示しています。授業単位で細かく指定するのではなく、ある程度まとまった範囲を示すことで、自分のペースで進められる余地を残しています。あまり細かく管理しすぎると、習熟度の差によって無理が生じるため、全員にとって無理なく取り組める水準を意識しています。
―運用の仕組みや、生徒への支援体制についても教えてください。
―今井先生
教材(Book)の作成は各教科が担当し、一度作ったものを毎年同じ時期・同じ範囲で配信しています。担当が変わっても引き継ぎやすい仕組みになっており、安定的に運用できています。
また、学習の状況は教科担任とHR担任が二重で確認・声かけを行います。可視化された進捗データをもとに無理のない範囲で「やらざるを得ない環境」を作ることで、生徒が自然に学習習慣を身につけていく。授業外での取り組みを主体としつつも、学校全体で支援する体制を整えているのが大きな特徴です。
さらに教科ごとに学年担当を決めており、担当者が週1回、学年全体の学習データを出力して整理・確認しています。web上の管理画面そのものよりは、出力データで進捗を把握し、完了状況は成績に反映。生徒は「取り組んだことが成績に直結する」と実感できる仕組みになっています。
活用ポイントまとめ ・英語を中心に据え、学習習慣を定着させる土台として活用 ・定期考査ごとの範囲を日割り配信し、生徒が自分のペースで取り組める設計 ・教材の継続運用と、教科担任+HR担任による二重の声かけで全校的に支援 |
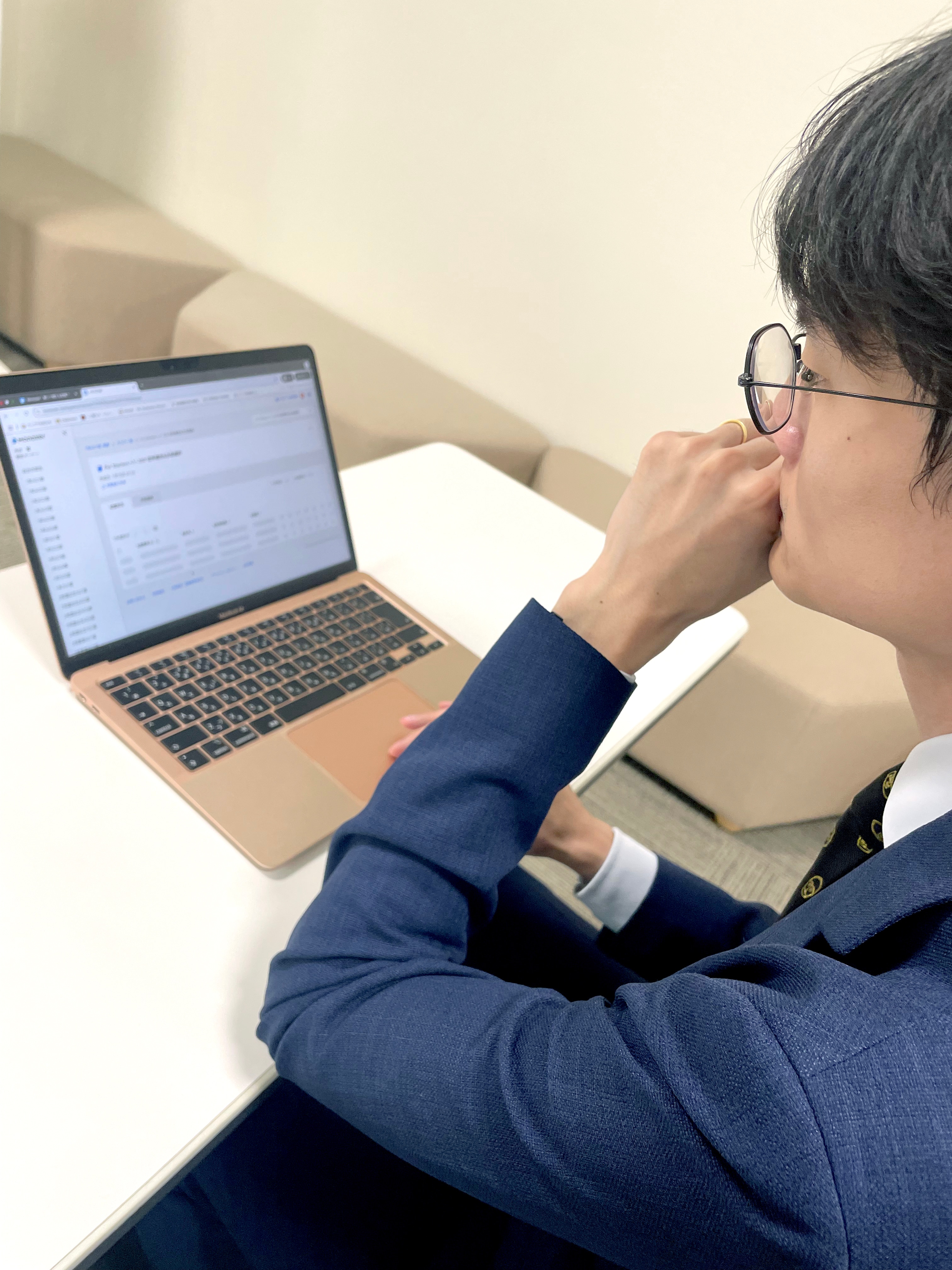
【活用のポイント①】無理なく続けられる学習量とペース設計
―Monoxerでの学習内容について、特にこだわっているポイントは何ですか。
―今井先生
そうですね、基本的には1日ごとの学習負荷が過度にならないようにすることをかなり意識しています。特に1年生は皆が同じペースで学ぶ時期なので、日々の学習量を調整しながら進めています。例えば日曜日は学習を休みにするなど、メリハリをつけて無理なく継続できる環境を作っています。
―1日の学習量や1期間あたりのエントリー数についてはどのように設定されていますか。
―今井先生
目安として、1エントリーあたり15単語くらいからスタートしています。学習の記憶度が上がるにつれて反復回数が増えるので、徐々に負荷は上がりますが、最終的には2倍、3倍になることもあります。それでも生徒が負担を感じすぎることはなく、無理のない範囲で学習を積み重ねられるようになっています。全体として、1期間でおよそ100単語/15日を越えないペースで進める計画です。
学習内容の量やペースを調整することで、日々コツコツ取り組む習慣を自然に身につけられるようにしています。無理なく進められるからこそ、生徒も継続しやすく、学習の定着につながっています。
【活用のポイント②】「やって当たり前」を作る仕組みとタイミングを活かした後押し
―生徒へのコミュニケーション、学習継続のためのモチベーション維持について、工夫されている点はありますか。
―今井先生
はい、モチベーションを無理に高めるというより、「やるのが当たり前」という感覚を作ることを意識しています。生徒には「ちょっとした時間でやるくらいならやろう」と、あえて抑えめのテンションで取り組むイメージを持たせています。もちろん、やらない子には強めに声をかけることもありますが、基本は当たり前の習慣として定着させることが狙いです。
声かけは主に、教科担当とクラス担任が連携して行っています。クラス担任は水曜日にロングホームルームがあり、その日に学習進捗をクラスに貼り出して共有します。生徒の習熟度を見ながら、やっていない子に適宜声をかけます。この声かけは週1回程度の頻度で行っています。
あとは生徒に対して、ただ「やろうね」「やってこい」と言うのではなく、例えば目標が25項目に対して現状が15項目で“遅れ”が出ているのならば、「今日からプラス2つずつすれば追いつけるよね」といった無理をさせず、かつ現実的なアドバイスを各先生方にも心がけてもらっています。
―どのくらいの期間で、生徒は自発的にMonoxerを活用するようになったと感じますか。
―今井先生
「当たり前だよね」という働きかけを継続すると、生徒も次第に自分で取り組むようになります。最初の1、2回の定期考査の段階で、ほとんどの生徒が自然と学習を進めるようになっています。ポイントは、やらない場合の指摘と、やる手間の方が少ないという感覚を刷り込むことです。こうした仕組みによって、1年生でも無理なく習慣化できています。
―ちなみに、今までは取り組めていなかった生徒が「当たり前に取り組むようになるきっかけ」は、どのように生まれていますか。
―今井先生
本校では、生徒が学習を始めるきっかけを意図的に作るようにしています。例えば、定期試験前後の面談や、夏季・冬季の三者面談など、年間を通して複数回の面談の場があります。こうしたタイミングで提出物の遅れや取り組み状況を指摘されることで、一旦「やらざるを得ない状況」になったのをきっかけに自発的にできるようになる生徒もいます。
また、進路ガイダンスやオープンキャンパス、修学旅行など、学年や学習段階に応じた節目を活かして、教員から温かいエールを送り、生徒自身が自然と「頑張らなければ」と思える外的要因を提供しています。このようにタイミングや状況に応じた教員の声かけや組織的な後押しもあって、生徒が自発的に学習を続ける流れを作れていますね。
活用ポイントまとめ ・「やるのが当たり前」という雰囲気づくりと声かけで習慣化を促進 ・進捗に遅れが出た場合は、日割り換算での巻き返しなど具体的かつ現実的な解消策を提案 ・面談や進路行事などの節目をきっかけに、組織的にモチベーションを後押し |
|---|

【活用のポイント③】担当制を通じた教員間の浸透と文化形成
―先生方のMonoxer活用を組織全体に浸透させるために、どのような工夫をされていますか。
―今井先生
学年ごとに担当者を決め、週1回で学年全体の学習データを集計する役割分担を設けています。また、わからないことがあれば確認できる窓口も用意しました。
導入当初は使い方にばらつきがありましたが、2〜3年の運用でMonoxerの存在が認知され、管理画面に抵抗がない層が増えています。基本操作や管理方法についても、はじめにMonoxer提供側による1〜2回の研修やオンライン説明を受けたので、主要メンバーはそこである程度理解できていましたね。
運用ルールとしては、アクティブ率や利用量に細かい基準は設けず、成績に組み込んで「提出物の一環」としたことで、自然に教員それぞれが責任をもって運用を推進していく文化が形成されたように思いますね。管理者間での振り返りは形式的には行わず、進めながら必要に応じて確認・修正しています。
【今後の展望】基礎から応用へ―習熟度に応じた段階的な発展
―今後のMonoxer活用について、どのような展望をお考えですか。
―今井先生
今後は、現在行っている取り組みを継続しつつ、学年や習熟度に応じて学習の負荷を段階的に強めていきたいと考えています。
具体的には、3年生では英作文を見据えた句や節単位の学習を取り入れ、単語学習だけでなく、文脈の理解や表現力の習熟も狙っています。すでに基礎レベルは「できて当たり前」の状態に到達しているため、上位層向けに質の高い内容に挑戦することで、学習の幅を広げ、効果的な反復学習も促進できるよう工夫していく予定です。






