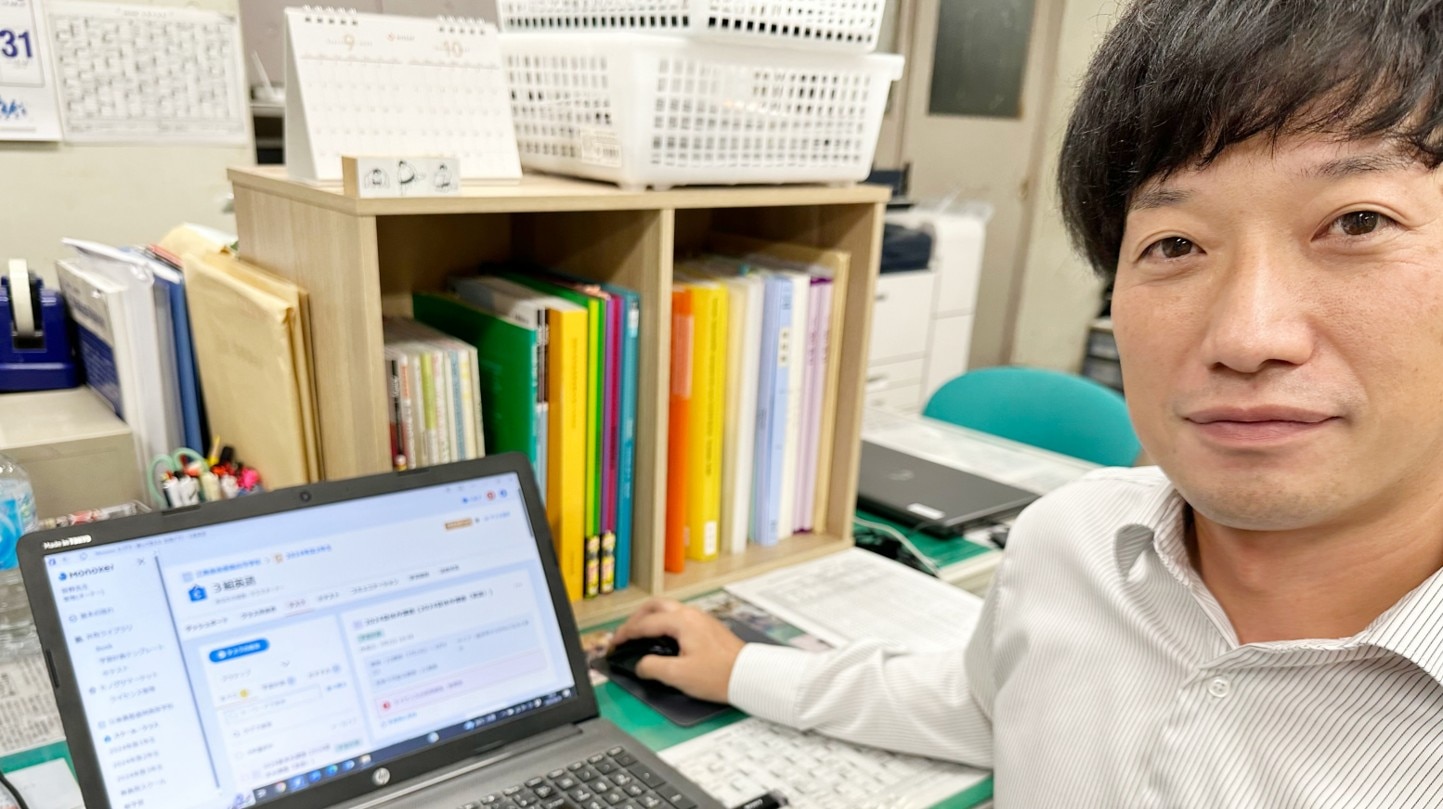
江南義塾盛岡高等学校様 活用事例 Monoxerで基礎学力の学びなおしを|誰一人取り残さない教育を目指して
🏫 お客様情報 岩手県盛岡市の私立高校で、創立130年を超える伝統校。教育目標に「30年後の大木を目指す『人間作り教育』」を掲げ、基礎学力や学習習慣を身につけられるよう生徒一人ひとりに粘り強く関わる。 ▼Monoxer活用シーン/科目 |
📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |
▼今回お話を伺った方

菅野 優介 先生 (教務課長・英語科主任)
教務課長として学校全体の学務を管理しながら、2年3組の担任、サッカー部の顧問、そして英語科主任をご担当。多くの役割を担う中で、警察官だった父親から教わった「誠実に」という言葉を大切にされているとのことです。休日には美味しいカフェを一緒に探したり、奥様と家でのんびり過ごすことを楽しみにされています。
目次[非表示]
【導入目的】誰一人取り残さない教育を目指して、Monoxerで基礎学力の学びなおしを推進
−まず、御校の教育の特徴と、なぜその中でMonoxerを導入しようとお考えになったのかについてお聞かせください。
−菅野先生
「30年後の大木を目指す『人間作り教育』」を教育目標に掲げる本校には、進学を目指す子から卒業後は就職を目指す子まで多様な生徒が集まっています。どのような進路でも、卒業から30年後と言うと48歳、ちょうど会社や社会の中核となるような年齢です。江南義塾の卒業生一人ひとりがその役割を担い、支えられる人になっていくことが私達の願いです。そのため、教育活動の中では「誰一人取り残さない」という点に留意しながら、まずは個々人に学習習慣と基礎学力を身につけてもらおうとしています。
そんな本校のMonoxer導入のきっかけは、毎朝10分行っていた朝学習です。もともとはB4両面印刷の基礎問題を配布して解かせ、日々ファイルに綴じさせていましたのですが、正直このアナログな方法はうまく行っていませんでした。「自分は1年間でこれだけの量を解いてきたんだ」と感じてもらうことを意図した取り組みだったのですが、ファイル管理がうまくできず、プリントが机の肥やしになって積み重ならない生徒がかなりの数にのぼっていたのです。
そうして「本校の生徒達にもっと合ったやり方はないか」とデジタル学習教材を検討して出会ったのがMonoxerでした。特に魅力的だったのは、学習の継続に負担感がなく、一番取り組みやすそうだった点です。これなら本校の生徒でも努力を積み重ね、その蓄積を見ることもできて良いのではないかと思いました。また、本校の朝学習は基礎的な漢字や計算問題、英単語などの学び直しを行っていましたので、教科をまたいで活用できる点も、英語などの単科目サービスと比較して魅力に映りました。
【効果実感】「勉強に向かう基本姿勢」を身につける生徒が増えた
−Monoxer学習を開始して、生徒にどのような効果があったと感じられますか?
−菅野先生
Monoxerのおかげで「勉強に向かう基本姿勢」を身につける生徒が増えたと感じています。これは私たち教員はもちろん、保護者の方も実感されていることです。保護者面談では「またスマホゲームをしてるなと思って画面を覗いたら漢字練習をしていて驚きました」というような声をよく頂戴します。
また、ここ1、2年で漢字検定を受検する生徒が増加したことも効果の現れかもしれません。受検級のグレードは高低まちまちですが、学習を続けることで「受検してみようかな」とチャレンジする気持ちが湧いてきているのは嬉しいことです。
勉強法の一つとしてMonoxerを「いいな」と思っている生徒が多数いる実感があり、導入してみて良かったと思っています。
今でもよく覚えているのですが、導入1年目、3年生の卒業する生徒から「先生、Monoxerを導入してくれてありがとうございました」と言ってもらったことがあります。その生徒は英語が好きな子でしたが、2年生までは英単語を覚えるために「ひたすらノートに書いて覚える」というやり方で努力してきた子でした。でも、3年生でMonoxerというツールを使って勉強するやり方に出会ったことで「自分が確かに覚えていっている」と達成感を味わいながら、楽しく勉強ができたんだそうです。
【活用方針】学習を習慣化する「朝学習×教科学習×長期休暇」のミックス活用
−御校は生徒全体のMonoxerの週間アクティブ率が常に6割以上で維持されていますが、その秘訣を教えていただけますか?
−菅野先生
まず、朝学習での活用がベースです。毎朝8時30分から40分までの10分間、漢字・計算・英単語など小中学校の学び直しとなる国数英の基礎問題に取り組んでもらっています。スキマ時間にも取り組むよう声がけはしていますが、それぞれのペースで学習を続けてもらうことが大切なので、進度や到達度に関してノルマは課していません。
ただ、「学習を続けることが成果につながる」と実感してもらえるように、毎週月曜日の1時間目に小テストとして確認問題を課していて、高い比率ではないですが評価項目にも入れています。また、長期休暇中の宿題もMonoxerで配信しています。
理科や社会など、他教科での活用は各先生にお任せしています。ただ、本校には「やる気はあるけどテスト勉強で何をしていいかわからない」という生徒も多いので、わかりやすい勉強法としてMonoxerでテスト範囲の課題を出してあげるのはいい方法だと思っています。例えば私の担当する英語科では英単語問題を配信してそこからテストに出すと約束をしています。もちろん、Monoxerを教科で活用した場合には、30点の平常点のうちの3〜5点満点程度で評価に入れるようにも各先生にお願いしています。
💡 活用ポイントのまとめ |

【活用のポイント①】タスクの「タイトル」や「ボリューム」を調整し、生徒が前向きに取り組めるように
−Monoxerで学習する生徒のモチベーション維持のためにどんな工夫をしていますか?
−菅野先生
まず、配信するBookのタイトルを必ず調整しています。もともと本校には小中学校の学び直しを行うという方針があり、授業自体もそうしたスタンスに従って行っています。基礎学力の土台をしっかり作ることは全員にとって重要なのですが、うまく伝えないと生徒のモチベーションを下げてしまいます。
例えば、MonoxerのBookはそのまま配信すると「中学1年」など学習範囲がタイトルになってしまうことが多いですが、過去の学習の学びなおしということを強調するよりも基礎知識の習得があくまで目的であることを強調したいため、本校では「英単語(基礎)」「基礎漢字」などのようなネーミングに変更することにしています。
もう一つは問題のボリュームの調節です。これは同僚の英語科の先生が特に上手に活用してくださっている点で、例えば英単語のBookを配信する場合も、頑張ればすぐ100%に到達できるような問題数にしてくれています。
私自身、自分の端末でMonoxerを試して最も印象に残ったのは「100%に到達したときの達成感」でした。これがMonoxerで一番楽しさを感じられる瞬間なんですよね。新1年生の授業でも、おとなしい男子生徒が「やっと100%に行けた!」と小さくガッツポーズしていたこともあるぐらい、生徒にとっても間違いなく嬉しいポイントです。私はつい最近100問テストを課して生徒の心を折ってしまったりもしたので、この「達成感まで生徒が辿り着けるようにボリュームを調節する」という工夫を見習いたいと思っています。
もちろん100%に到達することが全てではありませんし、進度に速い遅いがあるのも当たり前です。100%にならずとも、何度も挑戦している生徒の様子はパソコン上でもすぐ見てとれますから、生徒の学習に向かう姿勢をしっかりと評価してあげたいと思っています。
💡 活用ポイントのまとめ ✓配信するBookは基礎知識の定着の重要性・意図が伝わるように名称を変更 ✓100%の達成感を生徒が得やすいよう、問題数を適切な量に調整 ✓生徒の学習回数など、到達度以外の指標も評価する |
配信しているタスクの一例
【活用のポイント②】やらないデメリットではなく「Monoxerをやるメリット」を伝える
−生徒のMonoxerでの学習を支える上で、教員側から生徒へのコミュニケーションで意識していることはありますか?
−菅野先生
本校では生徒の特徴も鑑みて、「やらないと居残りにする」「平常点を減点する」といった"やらないデメリット"を強調するのではなく、「やった分だけテストの点数が上がる」「自分の将来に役立つ」という"やるメリット"を伝えるようにしています。
先日の始業式では、校長自ら「Monoxerをやれば必ず基礎力につながる」と生徒に語りかけてくれました。私自身もホームルームで取り組むメリットについての話をよくしています。先日はクラスの生徒の半数である就職を希望する生徒にも響いて欲しいと「Monoxerの配信課題のように、定められた課題に自ら取り組む姿勢が会社に入っても大切になるはずだよ」と伝えました。
声かけだけでなく、日常的に「やってよかった」と手応えを得てもらう場面づくりも大事だと思っています。週1回の小テストはもちろん、Monoxerで課題に取り組んでいる生徒を日常会話で褒めたり、スタンプを送信するのもその一環です。
ただ、この教師側のスタンプ送信についても「なるべく管理画面を覗いてスタンプだけでも押して下さいね」という声かけに留め、明確に頻度を決めて義務化することはしていません。導入当初は週1回必ず行うことにしていたのですが、どうしても先生によってブレがでてしまうので、そこは各々の先生にお任せすることにしたのです。
−長期休暇中はどの学校でもアクティブ率が低下する傾向がありますが、御校ではしっかり維持できています。何か秘訣などはあるのでしょうか。
−菅野先生
あまり特別なことはしていないですよ。登校日のホームルームで活用を促したり、休暇中にも管理画面を見てスタンプをちょこちょこと送ったりといったところです。登校日は実際に学習させて机間巡視することで「しっかりと取り組む姿勢を重視している」ことを伝えるようにしています。
あとは、これは私の場合ですが部長を務めているサッカー部の遠征中に、あまり進んでいない生徒にはちょっと声をかけて促しています。部活動はチームで意識を共有するものですし、同じチーム内ではしっかりやろうという意識が芽生えたと思います。またサッカー部は校内で人数が多いので、もしかしたら他の生徒への波及効果もあるのかもしれません。
💡 活用ポイントのまとめ ✓Monoxerをやらないデメリットではなく、やるメリットを伝え続ける ✓全体に対して校長や担任からMonoxer活用のメリットを伝える ✓長期休暇中も個別にスタンプ送信や部活動での声かけなどを行う |
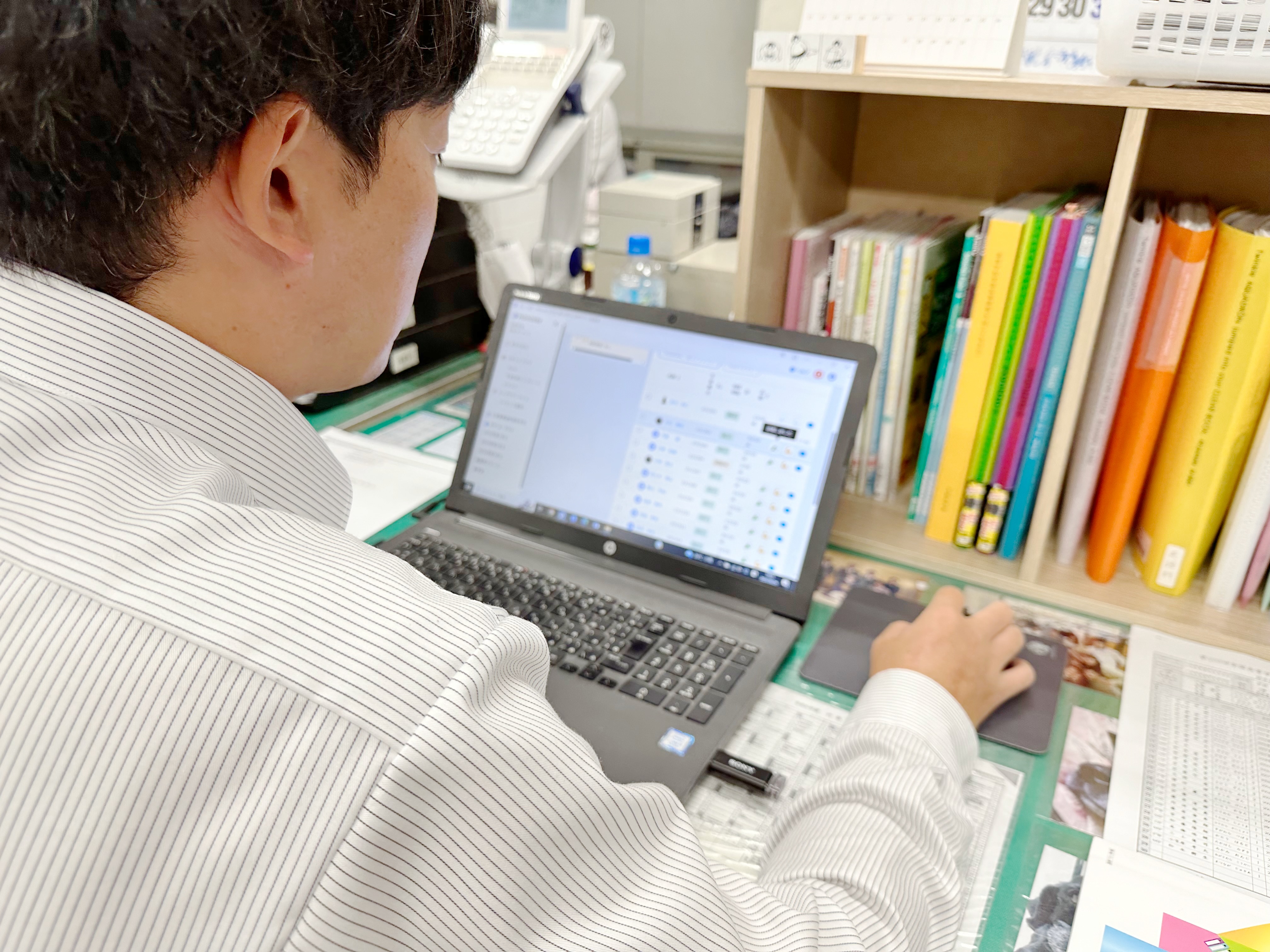
【活用のポイント③】まずは生徒目線でMonoxerを体感してもらい、他の先生に興味をもってもらう
−学校全体での先生方へのMonoxer普及の取り組みについて教えてください。
−菅野先生
全ての先生にMonoxerを活用していただくのが私の夢ですが、実際のところはまだ3割ぐらいかなと思っています。
特に導入で苦労したのはアカウント設定などの初期操作ですね。パソコンで設定を行うことにハードルの高さを感じる先生方は多かったので、私が設定したケースも多かったです。ただ「丸つけ不要で小テストの結果がすぐ見られる」「生徒一人ひとりの進捗・習熟の状況が一目で分かる」といった活用メリットは理解を得やすかったですし、運用上の操作も年配の先生が戸惑うほど難しくはありませんでした。
教師間での普及に関しては積極的に使ってくれている比較的若手の先生が起点になって、職員室の席の近い先生に勧めてくれて広げてくれています。
勧め方として良いやり方だなと思ったのは、興味を持ってくださった先生のスマホにアプリを実際に入れて体験をしてもらう方法です。実は、これで社会の先生が夏休みの課題をMonoxerで出すところまで活用してくださるようになったんです。実際に自分で問題を解いてみると「やっていくとパーセンテージも上がって面白いね」と気づいてくださるんですよね。そうやって、徐々に使う先生を増やしていきたいなと思っています。
💡 活用ポイントのまとめ ✓導入のハードルは初期設定なので、設定は代行するなど柔軟に |
今後の展望
−最後になりますが、今後の展望についてお伺いさせてください。
−菅野先生
本校の生徒にとって、Monoxerは義務やノルマではなく「努力が目に見える新しい勉強の仕方の一つ」です。
Monoxerの活用スタンスを大切にした上で、今後は生徒達の学習習慣の確立や基礎学力の習得を一層サポートできるような工夫を加えていきたいですね。一つのアイデアとしては、「同じクラスでこんなに頑張っている子もいるんだ」と刺激にしてもらえるよう、学習回数のランキングを示すというのも考えています。
さらに、大学進学をする生徒達も多いので、今よりももう一歩踏み込んだ「学習の質のレベルアップ」に向けた配信問題の検討や、教科の裾野を広げるといった取り組みもしていきたいです。






